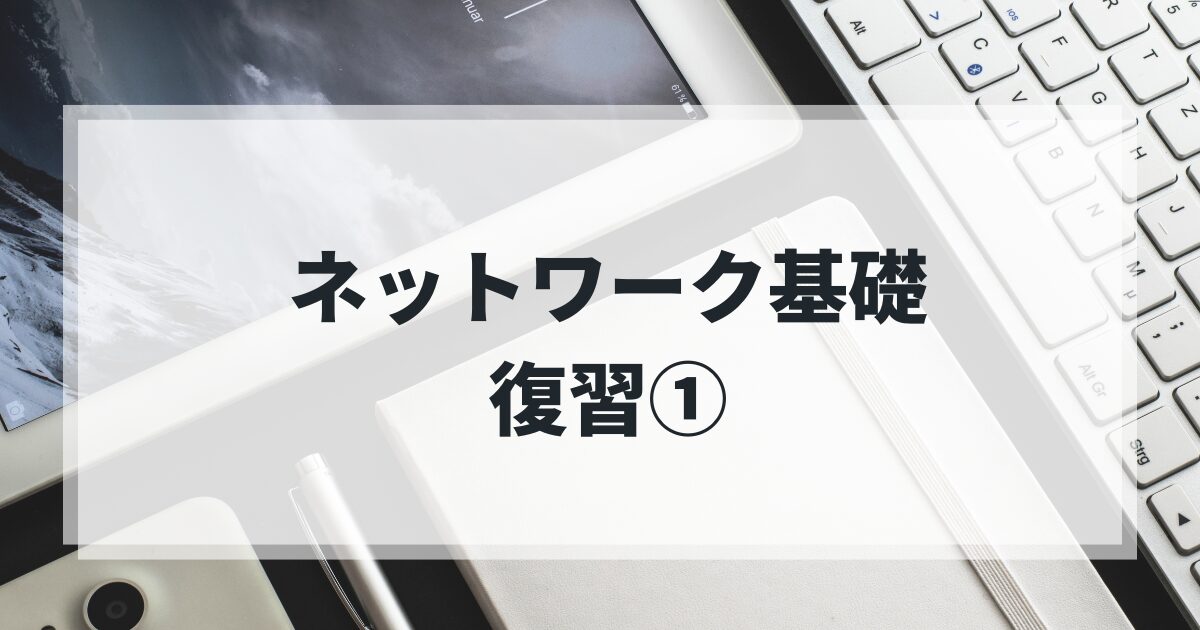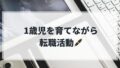こんにちは、Hiraです🌷
私は元々ネットワークエンジニアとして働いていましたが、今はフリーランス+育児の生活をしています。
最近「もっと自分の単価を上げたい」「案件の幅を広げたい」と考えるようになり、改めてネットワークの基礎を復習することにしました。
その第一歩が OSI参照モデル。
教科書に必ず出てくる用語ですが、正直「暗記で乗り切ったなあ」という記憶もあります。
この記事は、私自身の復習を兼ねてOSI参照モデルを整理したアウトプットです。
OSI参照モデルとは?
OSI参照モデル(Open Systems Interconnection)は、ネットワーク通信を7つの階層に分けて考えるモデルです。
通信の仕組みを理解するときに「今どの層の話をしているのか」を整理するフレームワークとして使います。
OSIの7階層
- 物理層(Physical Layer)
電気信号やケーブルなど、物理的な伝送部分を扱う - データリンク層(Data Link Layer)
MACアドレス、イーサネット。隣接する機器との通信を担当 - ネットワーク層(Network Layer)
IPアドレス、ルーティング。複数ネットワーク間で通信経路を決める - トランスポート層(Transport Layer)
TCP/UDP。通信の信頼性や分割・再送を管理 - セッション層(Session Layer)
アプリ同士のやり取りを維持(ログイン状態の管理など) - プレゼンテーション層(Presentation Layer)
データの形式変換や暗号化 - アプリケーション層(Application Layer)
実際にユーザーが触るアプリ(HTTP, FTP, メールなど)
私なりの覚え方
私は「上から順番に機能を積み上げるイメージ」で覚えるようにしています。
- 物理(ケーブル)
- データリンク(同じネットワーク内で通信)
- ネットワーク(異なるネットワークをつなぐ)
- トランスポート(通信をちゃんと届ける)
- セッション(会話を続ける)
- プレゼンテーション(翻訳や暗号化)
- アプリケーション(ユーザーが使う)
「階層を上るごとに“人間に近づく”」と考えると整理しやすいです。
実務で役立った瞬間
OSIモデルは試験用の暗記だけでなく、トラブルシュートの切り分けフレームワークとしてよく使っていました。
特に現場で多かったのは「第4層(TCP)」と「第7層(アプリケーション層)」の問題切り分け。
代表的な例が HTTP(ポート80)とHTTPS(ポート443) です。
80番は通るけど443番がダメ、というケース
- まず第4層のTCPでコネクションが張れるかを確認
- 80番(HTTP)はOK → 通信経路そのものは生きている
- 443番(HTTPS)はNG → この時点で「暗号化やアプリ層の問題」と推測できる
現場では「証明書やファイアウォールの設定に問題があるのでは?」と真っ先に疑うことがよくありました。
特に多かったのが FortiGateでの許可設定ミス。
80番は通るのに443番だけ通信できない、原因を調べると「HTTPSの通信がポリシーで許可されていなかった」ということが何度もありました。
もしOSIモデルを意識して「どの層で止まっているか」を冷静に考えていなかったら、
物理層やルーティングの設定を延々と疑って時間を浪費していたと思います。
まとめ:初心に帰ると見えてくるもの
OSI参照モデルは、ネットワークの基礎中の基礎。
でも「知ってるつもり」で放置していると、実務での応用力が鈍ってしまいます。
今回改めて復習してみて感じたのは、
- OSIはトラブルシュートのフレームワーク
- 「第4層か第7層か」を意識するだけで切り分けがスムーズになる
- 実務での判断力を支える基盤になる
ということでした。
最後まで読んでいただきありがとうございます😊
もし興味があれば、他にもこんな記事を書いていますので、ぜひあわせてどうぞ。